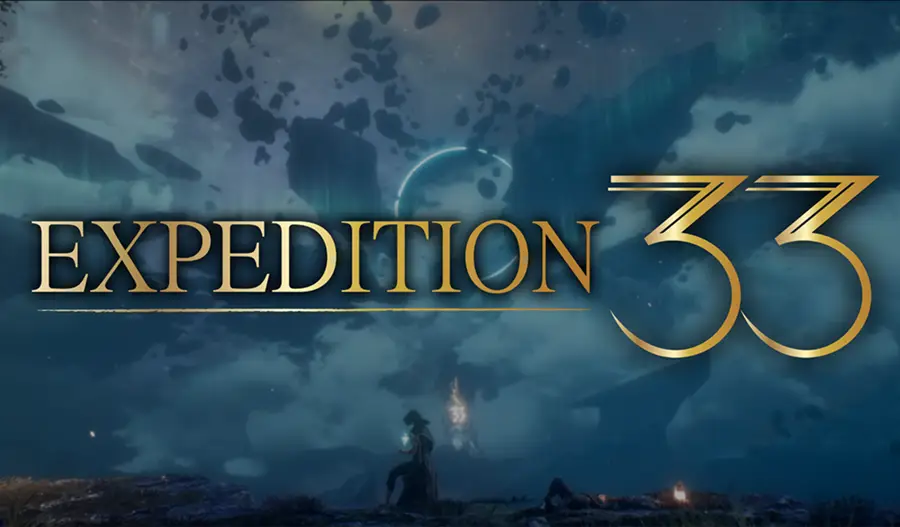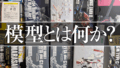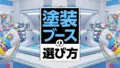わかりづらいストーリーで物議を醸しているEXPEDITION33ですが、ようやくクリアしたので感想などを書いていこうと思います。クリア前提の完全ネタバレになりますので、あらかじめご留意ください。また、1度をクリアしただけの状態ですので、伏線、設定の掘り下げなどは有識者におまかせし、個人的な視点による分析と所感とさせていただきます。
ストーリー概要
Googl Story Bookの機能で大まかな流れを絵本にしてみましたので、おさらいしたい方はご覧ください(PDF 1.5M)。

ゲームシステム
一応ゲームシステムについて触れておこうと思います。
ルックはペルソナのような戦闘画面で、最大3人までが参加可能です。最も特徴的なのは、敵の攻撃を『回避』と『パリィ』で完全に無効化できる点です。これは完全にアクションゲームの文脈であり、コマンドRPGに折り混ぜるというのは新しい試みだと感じました。

反面、粗が目立たないわけではありません。『回避』や『パリィ』によるダメージの無効化が前提となっているため、中盤以降の敵の攻撃はほぼ即死級になっています。結果として、キャラクターを強化していくRPG要素より、敵の攻撃を見切るための「覚えゲー」の側面が強いと言えます。極端な話、ゲーム中のほとんどの時間で、パリィしているといっても過言ではありません。

つまりどの敵と戦っても、パリィしてカウンターという戦略が同じということになります。もし『パリィ』による防御性能が段階的だったり、時にはパリィよりも有効な防御手段が用意されているというのであれば幅は広がったと思いますが…。単調なレベル上げ作業を省こうとした結果、それはそれで単調になってしまうという、若干皮肉な状況を生んでいます。もし次回作や類似システムが採用されるゲームがあれば、テコ入れされると期待しています。
世界観
ベル・エポック期の文化を彷彿とさせるビジュアルアートで構成されており、全編に渡り、美しい世界を堪能することができます。これは、この世界がアリーンの描いた絵の中であるということで、彼女の感性の世界を表現したものです。そのため、自然やありのままの美しさというよりは、人工物としての「整合性に支配されている美」とも言えます。

設定上、絵作りのテイストが統一されているため、ゲーム体験としては少々メリハリに欠ける部分もあります。これはビジュアルアートの問題だけではなく、先述の『パリィ』による戦闘の単調化や、ストーリー展開にも起因していると思われます。

いずれにしても、このゲームはこれまでの一般的なRPGと一線を画す世界観を有しています。特にストーリー展開については独特で、日本人には馴染みの薄い感覚や知識を前提としていると感じました。
世界を救わないRPG
EXPEDITION33は、一般的なRPGのように世界を救うゲームではありません。むしろ、そういったテンプレートに対するアンチテーゼ、あるいは対比とも言える内容です。

危険を犯して旅してきた世界は、全てアリーンが描いた一枚の絵の世界でした。そこに住む人間も動物も植物も、全ては絵筆によって描かれた架空の存在です。ですから、絵の中で倒した敵も、解決した問題も、全て架空のもので現実に影響しないものです。

この構造はさまざまな視点で見ることができると思いますが、一つはアリシアたちの架空の旅が、我々のゲーム体験そのものだということです。ゲームの中で経験したものは、どんなにリアルで美しく見えても、全て架空の用意された世界です。しかし、その経験は単なるストレス発散のエンターテイメントに止まらず、私たちの思想や哲学にどこか影響を与えているでしょう。アリシアたちも、この架空の世界の旅で、自身の心の問題に向き合うことになります。
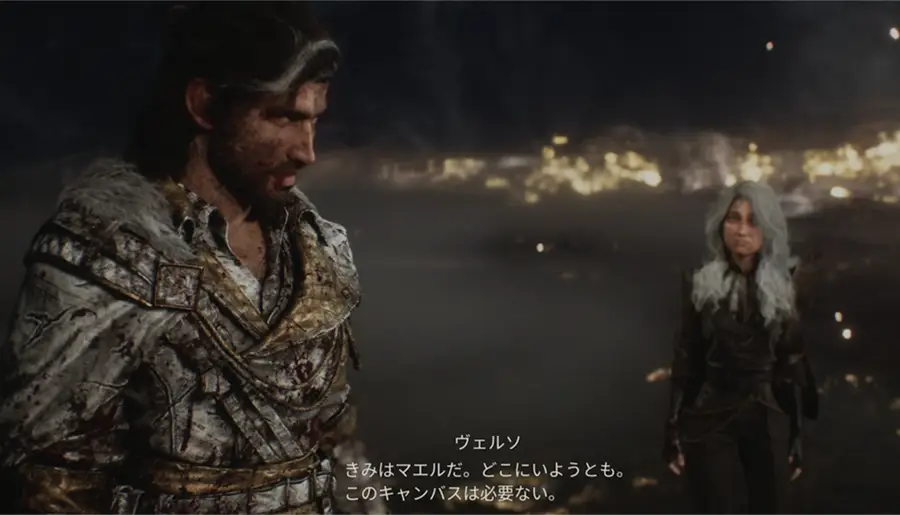
私たちの現実世界には、モンスターや用意された絶対悪は存在しません。多くの人が、日々仕事をし、大小の問題を抱え、自分の問題に向き合っていることでしょう。壮大な旅が家族の問題に集約していくのは、問題の規模の大小が、必ずしも個人にとっての問題の大小ではないということを表しているとも言えます。逆に言えば、規模の大きな問題であっても、結局は個人の心の問題に集約されるのではないか、という話でもあります。
個人主義を前提とした世界
このゲームはフランス製です。作者の背景についてはよくわかりませんが、圧倒的に日本人のメンタリティの外にあるということは感じました。それは、家族の問題を軸にしながらも、その実、登場人物のそれぞれが自分の問題にしか目を向けていないという点です。この物語の根底にあるのは、「個人の心の問題を解決することが世界の問題を解決することである」という感覚です。
アリーンはヴェルソを愛しているが故にキャンバスに執着しますが、アリシアやクレアにはほとんど触れません。絵画の世界のルノワールは現実より強面に描かれ、アリシアは火傷を負った現実の姿よりも醜く描かれます。悲しみや病んだ心がそうさせているとも言えますが、いずれにしてもアリーンがヴェルソと同様にルノワールを愛しているようには見えません。火事の原因の一端がアリシアにあるという事実を、まるで自身の汚点のように感じ、その心がアリシアを現実より醜い姿に描かせたのかもしれません。

ルノワールは最も理性的な行動を取りますが、アリーンの心を癒そうとはせず、絵の抹消という手段で強制的に現実へ引き戻そうとします。

クレアに関しては、アリーンに関与することにすら消極的です。

アリシアはヴェルソを気に掛けるフリをしながら、結局は自分にとって心地良い絵の世界を選ぼうとします。自分を庇って死んだヴェルソに申し訳なく思っていたり、感謝しているというよりも、ヴェルソの死の責任から逃れたいだけのようにも見えます。ですから、ヴェルソと意見が違えば、途端に自分の意志を貫こうと剣を向けます。

ヴェルソ自身もまた、アリーンやアリシアを助けるためではなく、自分が本来の死を得られる合理的な方法として絵の世界の抹消を望んだだけのように見えます。
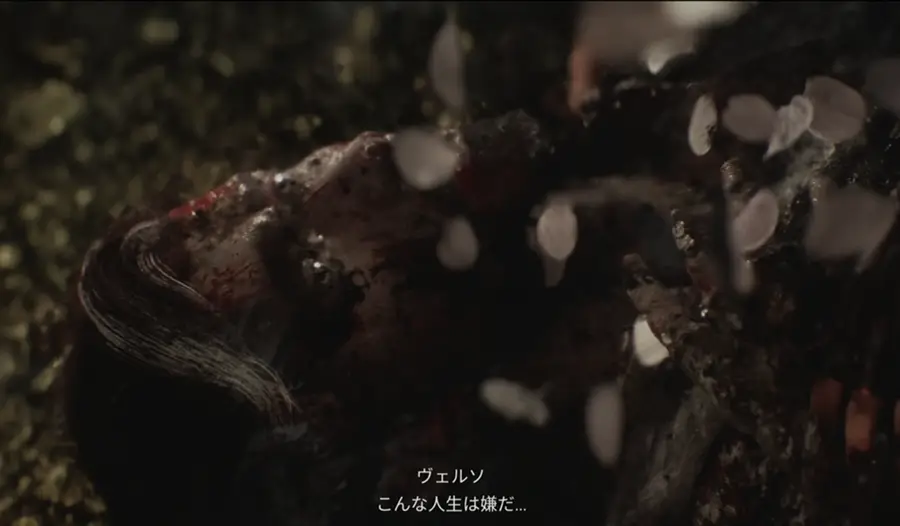
つまり、家族の中に利他性がほぼないのです。それぞれが独立した欲求によって動いており、自分のインセンティブを最優先にしています。この感覚が、日本人には少しわかりづらく、既存の物語の登場人物の不文律から外れていると感じます。
このキャラクター設定はもちろん意図的でしょうが、露悪的だったり、奇をてらっているようには見えませんでした。どちらかと言えば、製作者や想定しているプレイヤーのメンタリティに「圧倒的な個人主義」があり、それが自然に反映されているように思えます。
| 登場人物 | 最優先事項(自己の課題) | 家族への向き合い方 |
| アリーン (画家) | 悲しみの維持。罪悪感からの逃避と、ヴェルソの喪失という時間からの逃避。 | 娘(アリシア)の拒絶と、夫(ルノワール)との抗争。 |
| ルノワール (作家) | 理性の維持と肉体、家族という体裁の保護。アリーンの肉体という「現実」の維持。 | 妻の感情を無視した強制的な介入(抹消)。亡き息子(ヴェルソ)との和解の放棄。 |
| ヴェルソ (息子) | 真の死と安息。永遠に悲しみの原因であることから解放されること。 | 娘(アリシア)を「目的達成の道具」として利用。父親(ルノワール)との協力拒否。 |
| アリシア (娘) | 自己の安寧とアイデンティティの確立。現実の傷からの逃避。 | 両親の葛藤への無関心と、自己救済の優先。 |
一般的な日本人の道徳観念からすると、忌避されかねない行動原理です。この動機が「問題点を含んだマイナススタート」ではなく、「ナチュラルなゼロスタート」であると考えればしっくりきます。おそらく西欧文化圏の人間に共感される、ベーシックなメンタリテイにチューニングされているのだと思います。
キリスト教と対峙してきた西洋の思想と哲学
日本は島国であり、客観的に見てかなり特殊な文化を醸成してきたと言えるでしょう。反面、多くの大陸国家は、移民や多様性という問題点をクリアしなければなりませんでした。言葉や文化の壁を超え、一つの国としてまとめるには、「圧倒的な権威」という強制力が必要だったとも言えます。しかし科学や文化が発達しはじめると、その権威に更なる説得力が必要になってきます。それが西洋哲学の流れです。個人主義と実存主義(自己の存在意義や自由意志を重視する哲学)の影響を強く受けているのがフランス人のベーシックなメンタリティと言えるかもしれません。
| 段階 | 思想家(例) | 神に対するスタンス | 影響 |
| 初期近代 (17世紀) | デカルト | 「神の存在は理性の力で証明可能である」。神を否定せず、理性の権威を確立しようとした。 | 「私(自己の意識)」が世界の認識の出発点となる個人主義の確立。 |
| 啓蒙主義 (18世紀) | カント | 「神の存在は理性で証明できない」。道徳の根拠を神ではなく人間(理性)の内側に求めた。 | 宗教的な権威を人間的な理性から切り離し、世俗化を推進。 |
| 後期近代 (19世紀) | ニーチェ | 「神は死んだ」と宣言。キリスト教的な価値観の崩壊を指摘し、超人による新しい価値創造を主張。 | 「神の否定」が明確な哲学的主題となり、実存主義の思想に繋がる。 |
結果として、彼らの多くはキリスト教徒でありながら、それと両立する形で個人主義を醸成していくことになります。フランスにおける世俗主義(ライシテ)も同様の流れを組んだものと理解できます(AIまとめ)。
東洋哲学との比較
近代化の流れに伴って発展した西洋哲学の流れは、我々日本人が持つ伝統的なメンタリティと大きく異なります。もちろん育った環境な年代によって個人差はあるでしょうが、大筋を比較するとわかりやすいかと思います(AIまとめ)。
| 要素 | フランス的な実存主義/個人主義(極端な場合) | 伝統的な東洋哲学(仏教・道教など) |
| 世界の中心 | 自己(個人の意識と自由) | 縁起/関係性(全ては繋がっている) |
| 自己の定義 | 孤立した意識。自己の意志で世界に意味を与える。 | 流動的な存在。他者との関係性の中で自己が定義される。 |
| 救済/安寧 | 個人の内面の葛藤の解決(自己救済)。他者や世界は二義的。 | 自己の「小我」の否定。世界との調和(大我)の中に安寧を見出す。 |
| 『EXPEDITION33』との関連 | アリシアの「自己の安寧」が、家族や世界の真実よりも優先される。 | 家族や世界の真実との調和が、個人の安寧の前提となる。 |
| メッセージ | 「私」が救われれば世界は安定する。 | 「私」を捨ててこそ世界は安定する。 |
この対比から、『EXPEDITION33』で示された「自己の心の安寧を最優先し、他者や世界の犠牲を容認する」という思想は、「自己を捨てて全体との調和を目指す」という東洋哲学(特に仏教や儒教)とは、価値観の優先順位において真逆にあると言えます。
ちなみに、東洋には小乗仏教のような考え方もあるため、そちらとも比較してみました(AIまとめ)。
| 要素 | 小乗仏教(上座部仏教) | 『EXPEDITION33』の思想 |
| 救済の目的 | 個人の悟り(阿羅漢)。煩悩からの解脱。 | 個人の心の安寧(トラウマからの逃避/解決)。 |
| 「内的な問題」への焦点 | 共通点:外部世界よりも内面の修行を重視する。 | 共通点:内的な問題(アリーンの悲しみ)を重視する。 |
| 家族/他者の扱い | 家族や愛着は「煩悩」として切り捨てるべき対象。 | 家族は「愛着」であり、救済の最も重要なインセンティブ(ルノワールやヴェルソの動機)。 |
| 自己と世界 | 自己の煩悩を消すことで、世界から離脱する。 | 自己の感情を満足させることで、世界を安定させる(支配する)。 |
似ているようでやはり違いますね。小乗仏教がより観念的な自己解決を模索するのに対して、西洋個人主義は、自分や家族(他者)に対して具体的で積極的なアプローチで対応しようとしているように思えます。
2種類のエンディングが示す意味
EXPEDITION33のストーリーは、先述のような西洋文化における思想の流れを理解しておかないと意味がわかりづらいのではないかと感じます。つまり、前提として強烈な個人主義があり、それに対しての疑問や問題点を、彼らが常に抱えているのではないかということです。だからこそ、このストーリーにより強いテーマ性を感じるのかもしれません。
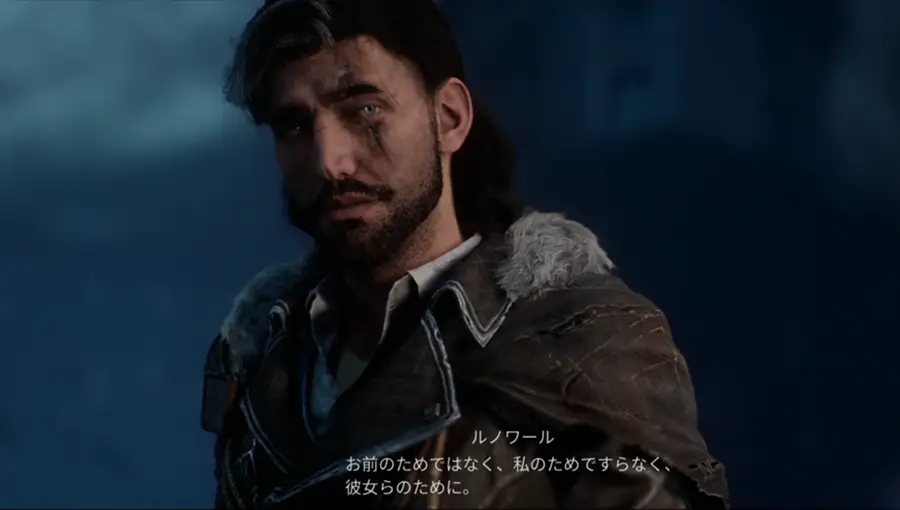
2種類のエンディングはどちらもスッキリしないものになっています。火事で声を失ったアリシアは絵の中に自由を求め、現実と向き合いたいルノワールとヴェルソは絵の抹消を望みます。いずれにしても、アリシアかヴェルソのどちらかの願いはかないません。(個人的にはヴェルソEDがグッドエンドだと思っていますが)

これまで家族のそれぞれが個人の行動原理を優先してきた結果、それが招いたものとしてこの2択が用意されたということは、何を意味するのでしょうか。
ドラクエやFFでは、主人公たちは我慢をして使命を貫き、他者のために働き、世界を救済します。皆、利他的な善人という枠に嵌められていると言ってもいいかもしれません。実際、物語の中だけに存在するギュスターヴやマエル(アリシアの記憶を取り戻す前)は、比較的善人ムーブです。しかし、それらは本当にリアルなのか?と疑うのも無理もありません。

実際の世界では、身勝手で利己的な人間が多いのは事実です。そして、誰しもがそうなってしまう危険性を孕んでおり、抵抗しようのない状況に置かれることもあるでしょう。EXPEDITION33では、ある意味でそのリアリティに触れています。窮地に追いやられた人間は、利他性を優先することができず、性善説や理想論を前提としているような思想では問題は解決されない。個人の意志と能動的なアプローチだけが問題を解決するのだと。

しかし、だからこそ、それが招く2種類のエンディングにもリアリティとメッセージ性があります。もしこのスッキリしないエンディングが意図的なのであれば、このゲームの結末は、行きすぎた個人主義や西洋文化の独善性に対するアンチテーゼと取れなくもありません。

だとすれば、原始的な宗教が訴えていた「隣人愛」などの「幸福と社会秩序を生むための哲学」への回帰を示唆しているようにも思えます。もしかしたら、EXPEDITION33は、西洋哲学が培ってきた「神と対峙」を問い直しているのかもしれません。
最後に
まだ1度クリアしただけなのでよく理解していない部分も多いかと思いますが、現段階での所感をまとめてみました。
少し批判的な内容に見えたかもしれませんが、個人的にはJRPGがリスペクトされ、これほどのゲームが海外から発売されたということは、とても喜ばしいと感じています。
絵画的なビジュアルアートと、伝統的なRPGのシステム、そして死にゲーや覚えゲーといったアクション要素が組み合わさり、なんとも独特なゲーム体験を得られる作品でした。
続編も是非期待したいですね!